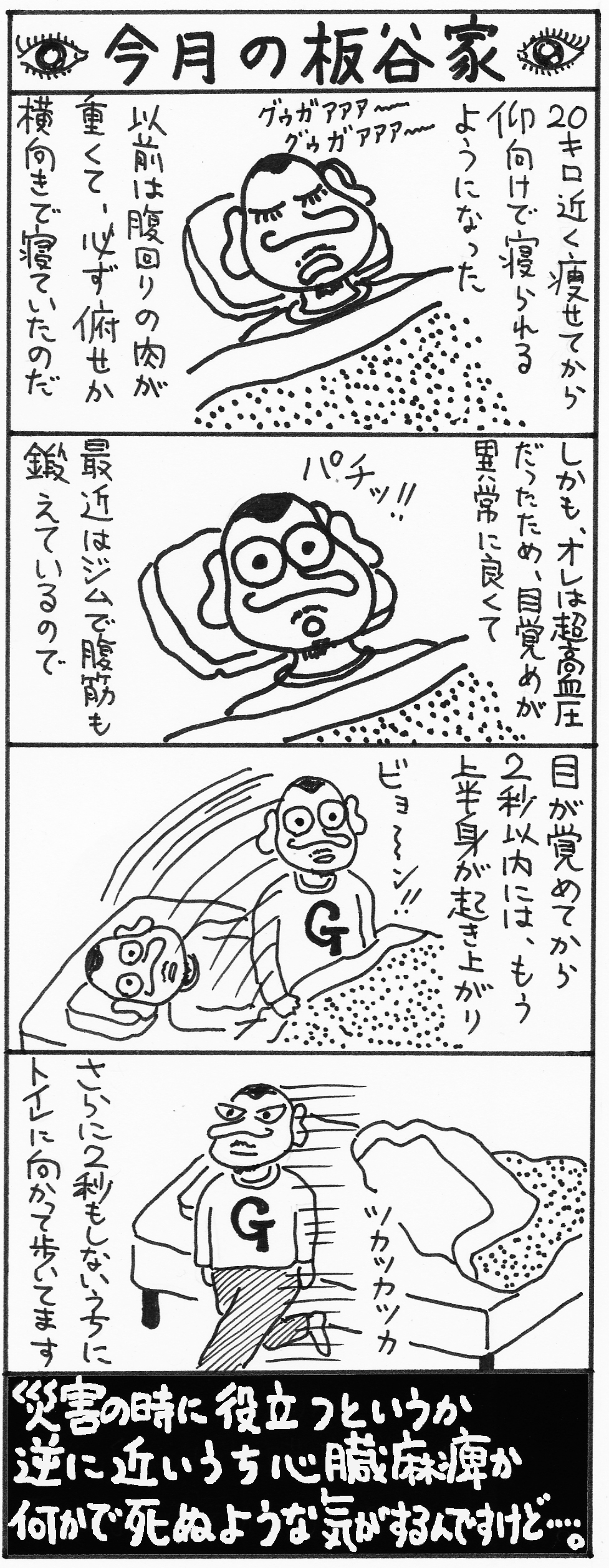少年になった輝貴(後編)
「あれっ……誰? この少年は」
オレんちに勝手に上がりこんできたかと思うと、スグに今のテーブルに着いてる輝貴に視線を止め、そんな言葉を発するキャーム。
しかし、このキャームという男は、頭の中に天然のセンサーでも内蔵してんのか……。てか、2~3年前からオレは「キャームを休もう週間」に入り続けているので、最近会うといったら月に1回ぐらいのもんで、それだって勝手にキャームがオレんちに来るだけなのだが、また、そういう時に限って直舌のケイコが来ていたり、今回のように以前キャームが号泣させた輝貴がたまたま来ているのだ。ねぇ、どうして!?
「あっ……お前って昔、大泣きしたあの頭の形が超不格好なガキかぁ~!?」
キャームにそんな大声を掛けられた途端、オレの隣で「カ、カラス……」というつぶやき声を発し、あろうことか、微かに震え始める輝貴。
「おいおい、何だよ、お前。もうすっかり少年になってるじゃねえかよっ。もうセンズリはもちろん、ブスな女とも1~2回はヤッちゃったのか!?」
「あっ……あの………」
困った表情で、そんな言葉をキャームに掛ける久美ちゃん。
「あっ……アナタがお母さん? お母さんも大変でしょ、こういうちょっとでも隙を見せるとスグにポコチンをシゴいちゃう息子を持つと」
「おいっ、キャーム!」
思わず言葉を挟むオレ。
「つーか、お前ってもう高校生?」
そう言いながら、イスを引いて輝貴の正面にドッカリと座るキャーム。
「そ、そうだし……」
「で、彼女はできたのか?」
「そ、そんなもん、いねえし……」
「なんだ、さっきからその『し』っていうのは? ま、いいや。じゃあ、童貞か、お前は?」
「う、うるせえよっ! なっ……なんでそんなことをカラスに話さなきゃいけねえんだよおおおっ!!」
血の気が完全に引いた顔でブルブル震えながらも、キャームを怒鳴りつける輝貴。
「テ、テルちゃん。カラスって誰なのっ?」
そんな質問を興奮している輝貴に飛ばす久美ちゃん。
「つーか、お母さんはちょっと黙ってて!」
そう言って久美ちゃんに釘を刺すと、再び正面の輝貴の方を向くキャーム。
「じゃあ、お前はTVゲームとセンズリばっかりコイてんのか?」
「そ、そんなことしてねえしっ!!」
「じゃあ、何やってんだよっ? 女装とかして、自分のオッパイでも揉んでんのか?」
「ちょ……ちょっとっ、何を言ってるんですかっ、アナタは!?」
堪らず、再び言葉を挟んでくるキャームの隣に座ってる久美ちゃん。
「だからっ、今は男同士の話をしてんだから、お母さんは黙ってて!」
そんな言葉を横を向いて飛ばした後、再び正面に向き直るキャーム。ちなみにこの時、オレも言葉を挟んでキャームを止めようとも思ったが、やっぱり止めておいた。もう、こうなった以上、ブン殴りでもしない限りはキャームは止まらないだろうし、これで久美ちゃんと付き合いがなくなっても、それはそれでもう仕方がないと思ったのだ。
「じゃあ、お前は何が趣味なんだよっ、え?」
「し、趣味なんて無えしっ」
「じゃあ、なんで生きてんのっ?」
「べっ……別に理由があって生きてるわけじゃねえしっ」
「じゃあ、アレか。街中とか歩いてて、自分好みの女が正面から歩いてきたら(うわっ、あの娘、萌えだし!)とか思いながら、家に帰って、その女に自分が縛られてるところを想像しながらオナニーするのが楽しみなのか? えっ? えっ?」
「だきゃらっ、そんなんじゃねえし!!」
そう声を荒げたかと思うと、テーブルの上を右手でヒステリックに叩く輝貴。
「じゃあ、アレか。日曜日にバカが集まる秋葉原のAKBショップとかに行って、好きなメンバーの名前が入ったタオルとかを買って、夜寝る前にそのタオルを顔にかぶせながらオナニーするのが楽しみなのか? それでイク時に『クフゥ~~~~~』とかって情けない声を上げるのかっ? そうなのか?」
「このオヤジ、ふざけんじゃないぞおおおおおっ!!」
あろうことか、そう叫びながら隣にいるキャームに掴みかかっていく輝貴。すると、次の瞬間……、
ブゥバチチチチチ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ンンン!!
それより一瞬早く、輝貴の左頬に炸裂するキャームの猛ビンタ。そして、真顔に吹っ飛んだ後、何かを猛烈な勢いで考えているような表情をしてから、思いっきり声を上げて泣き始める輝貴。その声はビックリするほど低い変な声で。正直聞いてるだけで胸がムカムカする響きを湛えていた。
「ほらっ、テルちゃん、早くおいで! もうココには2度と来ないからっ」
それが久美ちゃんは発した、多分オレが聞く最後の言葉だった。
なぁ、キャームラ先生……。君に対するお休み期間、あと1年間延長っ!