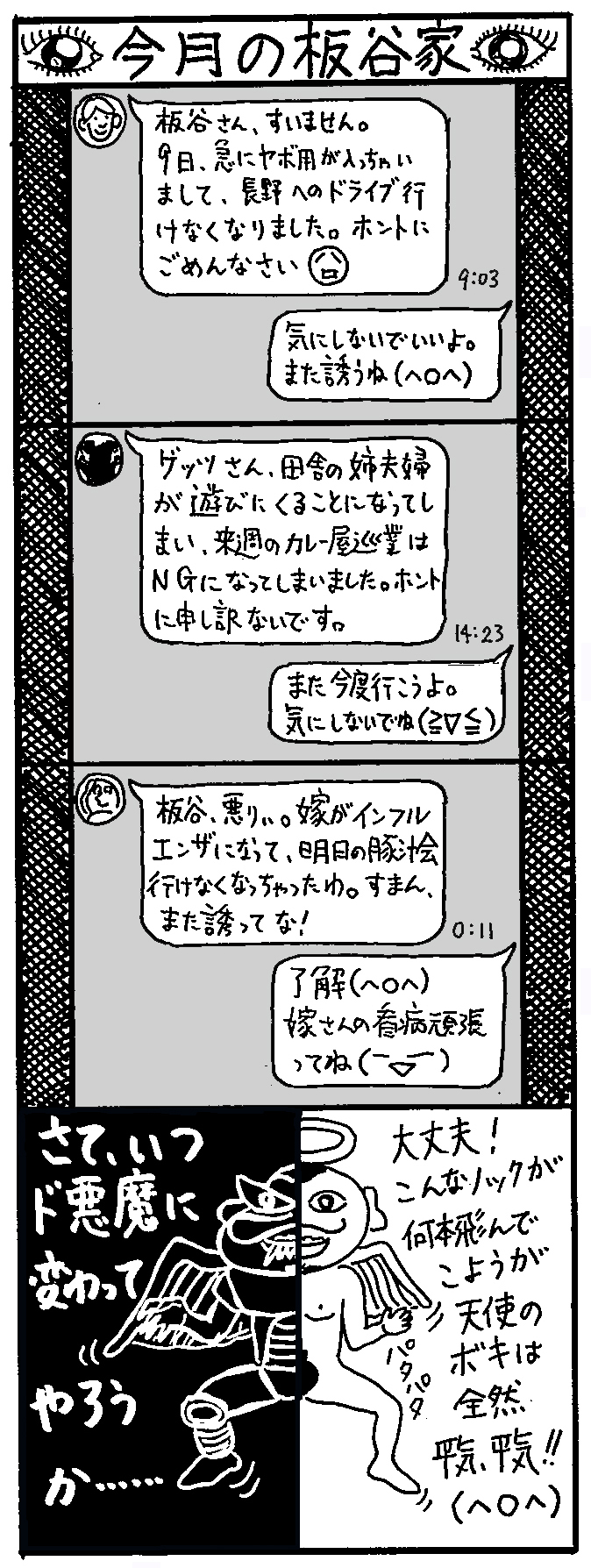外人パーティ国交断絶記(後編)
横浜のクラブで開催されているダンパ(ダンスパーティ)、そこにオレの友達の高橋の案内で乗り込むことになったオレ、高橋、キャーム、ハックの4名。しかも、今回オレたちはイギリス女と2名の日本女を同伴したのだが、そのイギリス女はスタイルは抜群だったが、顔がケント・フリックという爬虫類系の音真似芸人にソックリという始末で、あとの2人も1人は風邪を引いているポッチャリ女、そして、もう1人は見てくれはそんなに酷いわけではなかったが、とにかく精神的な危うさを感じさせる女だった。で、オレたちは彼女たちの名前も知らなかったので、イギリス女には「ケント」、ポッチャリ女には「ドラミ」、危うさを感じさせる女には「脱獄」というアダ名を付けたのだった。
「へぇ~、このクラブは2階に席があって、踊り場は1階なんだ」
そのクラブの2階にあるソファの1つに腰掛けると、ソコから下にある踊り場を覗き込むようにして、そんなセリフを吐くキャーム。
「うわっ、あの娘、もう本領を発揮してるよ」
続いて高橋がそんなセリフを吐いたので、奴の視線を追ったところ、少し離れたソファのアメリカ人らしき男が3人腰掛けてる席に早くも脱獄が座っており、しかも、その3人のアメリカ人たちに肩や髪の毛をベタベタと触られ、ウットリした表情を3人に向けていた。
「ギャムくん、アタシたちは踊ろうよ!」
突然そんなセリフを吐いたかと思うと、隣にいたキャームの手を取り、強引に下の踊り場に誘導していくケント。そして、1分もしないうちにケントとキャームが向かい合って踊り始めたのだが、キャームは両手の指をポール牧のようにパチパチと鳴らし、下半身はただ前後に動くステップを踏んでいるだけで、踊っているというより、ダメなマジシャンが時間を潰してるだけのような動きなのだ。で、普通なら自分の幼馴染みのこんなダンスを目の当たりにしたら絶対爆笑するのだが、この時のオレは別の意味で心の中で爆笑していた。
そう、奴は自分のダンスがオカしいかオカしくないかの判断の前に、爆裂に迷っていたのである。もう1度言うがケントのスタイルの良さはハンパじゃなかった。しかも、背も170センチ近くあり、長く伸びたソバージュヘアーもその魅力にターボをかけていた。
が、顔はケント・フリックなのである。オレからすればそれだけでアウトなのだが、元々スタイルのいい西洋人にはキャームは憧れのようなものがあって、しかも、その西洋人に超積極的に踊り場に連れ出されたのだ。そう、つまり、その時のキャームには、あまりにも早い展開で、ありか無しかを冷静に判断する余裕が全く無かったのである。で、そうこうしているうちに1階の踊り場が急に暗くなり、チークタイムに突入。そして、改めて奴らのことを見ると、ガップリと抱き合いながらゆっくりと左右に揺れていた。
そんな2人の姿を見て、オレも急に自分のことを考えるようになった。と言っても残っているのはドラミだけで、まぁ、この女とヤッちゃおうかとも思ったが、コイツは風邪も引いてるしなぁ……。
「踊っちゃう?」
オレの心の声が聞こえたかのように、そんなセリフを掛けてくるドラミ。
「いや、オレは……あ、ハック。お前、このドラミ……じゃなかったっ、お、おねーさんと踊ってこいよ、な!」
間もなくして、並んで下に降りていくドラミとハック。踊り場ではチークタイムも終わり、再び派手な曲が流れ始めていたが、このドラミとハックの踊りも普通じゃなかった。ドラミは風邪っ引き&ポッチャリ体型にも拘わらず、ハンパなく機敏なブレイクダンスのような踊りを繰り出したかと思えば、ハックは右脚と左脚の骨が折れたのを庇うような、とにかくリズム感を感じさせない、子供時代に親に買ってもらったことのある、あの竹で出来た田舎玩具のヘビのような動きをしているのである。冗談抜きで、オレが今までクラブやディスコで見た1番変な踊りだった……。
「コーちゃん、帰るべよっ」
ハックの踊りを見ながら1人で笑っていると、突然耳元でそんな声がした。キャームだった。
「えっ……何で?」
「さっきまでケントとチークを踊ってたんだけど、ハンパじゃねえよ、あの女。口からラクダの肛門みたいなニオイがするんだよ!」
「ラ、ラクダの肛門!?」
「そうだよっ。だからチークの時、ズ~~っとアイツの真横に自分の顔を並べてたよ! もう帰ろうぜ、な!」
「い、いや、ちょっと落ち着けよっ、な。オレ、ちょっとトイレに行ってくるから」
そう言って立ち上がると、オレはトイレに向かって歩を進めた。そう、こういう時はキャームのペースに巻き込まれずに、まずは一息ついた方がいいのだ。
「YES、YES!!」
男子トイレの中に入ると、奥の個室の方からそんな女の声が聞こえた。思わずオレは慌ててトイレの外に出て、改めて表札を見ると、あれっ、やっぱり男子トイレだよなぁ……。
「YES、YES!! FUCK ME!! YES、YES、YES!!!」
再びトイレの中に入っていくと、先程より更に激しくなっている女の声。
(うわっ!!)
個室の扉の隙間、そこからショッキングピンクのようなモノが見えた瞬間、オレは思わず声を出しそうになった。それは確か脱獄が着ていたブラウスの色で、つまり、あの個室の中では………てか、何ていう分かり易い女なんだろう、あの脱獄って。
トイレから自分の席に向かってる時に、途中にある大きな柱の脇に高橋がカクテルグラスを持ちながら立っていたので、とりあえずオレは今後のことを奴と相談することにした。
「お前、結局あのイギリス女と付き合ってない理由は、やっぱアイツがブスだからだろ?」
「まぁ……でも、こういう合コンの時には、あのイギリス女が色々な女を連れてきてくれるんだよ」
「で、それが今回のドラミと脱獄かいっ? てか、今トイレに行ったら、個室の中で脱獄が外人とSEXをしてたぞ」
「あ~あ……」
「もう別の女を狙うからな、オレたち」
その後、自分の席に戻ると、そのソファにはキャームとハックが座っていた。
「なぁ、コーちゃん。マジで帰ろうぜっ。こんなところにいても意味ねえよ!!」
「てか、最初に言ったけど、お前、せめて一次会が終わるまでは……」
「いや、一次会が終わるも何も、ケントや脱獄は問題外だし、ドラミもハックと引っ着くかと思ったら、急に外人男に話し掛けて向こうのテーブルに行っちまうしさっ」
そう言ってキャームが指差す方を見ると、なるほど、そのソファの席ではドラミがドイツ人ぽい男にダラダラした感じで笑いかけていた。
「アナタとヤッてもいいけど2万円ちょうだい、って言われたんスよ。で、そんな金は持ってないって言ったら、アッチのテーブルに行っちゃったんです……」
そう言いながらタメ息をついているハックを見た後、このクラブの各所を改めて見渡してみると、外国人の女は殆どおらず、まさに日本のブス女たちが外国人の男を漁りに来てる感じだった。
「ほらっ、コーちゃん。とっとと帰るぜ!」
そう言うと、オレの腕を引っ張って立ち上がらせるキャーム。この時のオレは、それに抗う気持ちは残ってなかった。
「あっ、板ちゃん、ドコ行くの!?」
(板ちゃん?)
1階の踊り場脇の通路を歩いている途中、不意にそんな声を掛けられ、視線を踊り場の方に向けるとケントがこちらを見ていた。
「ねぇ、ドコ行くのぉ!?」
オレの真横まで万引きの補導員のような勢いで来ると、再びそんな質問を放ってくるケント。その感じからして、オレたちのことは逃がさないわよ、という圧力が彼女全体から漂っていた。
「いや、はっ……腹減ったから、ちょっと外でメシ食ってくるよ!」
「え、食べ物ならココにも沢山あるじゃない!」
「いや、オレ……あの、その……お、おでんみたいなモノが食べたいからっ……す、すぐ戻るよ!」
そう言って、既に肩に回されていたケントの手を振り払うオレ。と、すぐにそのケントが顔をオレの真ん前に持ってくると、次のようなことを耳打ちしてきたのである。
「ワタシのオマンマンも食べごろだからねっ」
(うげっ、キャームの言った通り、ホントにケントの口って肛門のニオイがする!!)
数分後。キャームとハックと一緒に自分の車に乗るオレ。
(悪いな、高橋。でも、今日だけは黙って帰るわ)
そう思いながら、アクセルを強く踏んだ次の瞬間だった。
「あびゅなあああああ~~~~~~いいいいいっ!!」
突然、助手席からハックの絶叫。反射的に今度は急ブレーキを踏むと、車のフロントガラスのすぐ前に高橋の姿が!!
「おい、どっ……どこ行くんだよ?」
泣きそうな顔で、そんな質問を飛ばしてくる高橋。
「いや……ちょっとおでん食べてくるよ! す、すぐに戻るから!」
帰りの車内は爆笑で溢れていた。バックレた理由は、おでんが食べたかったから。それがツボにハマってしまい、オレたち3人は笑い狂いながら立川へと向かった。数日後。高橋から再び「今後は、俺とイギリス女と板谷と、もう1人、マブい女を誘わせるから六本木のクラブに行こうよ」という電話が掛かってきたが、オレは丁重に断わった。
“ワタシのオマンマンも食べごろだからねっ”
てか、口が肛門のニオイがする女って、アソコはどんな恐ろしいニオイがするんだよっ!?
今も2年に1度ぐらいの割合でケントの顔を思い出すが、その度にオレはえずきそうになる。