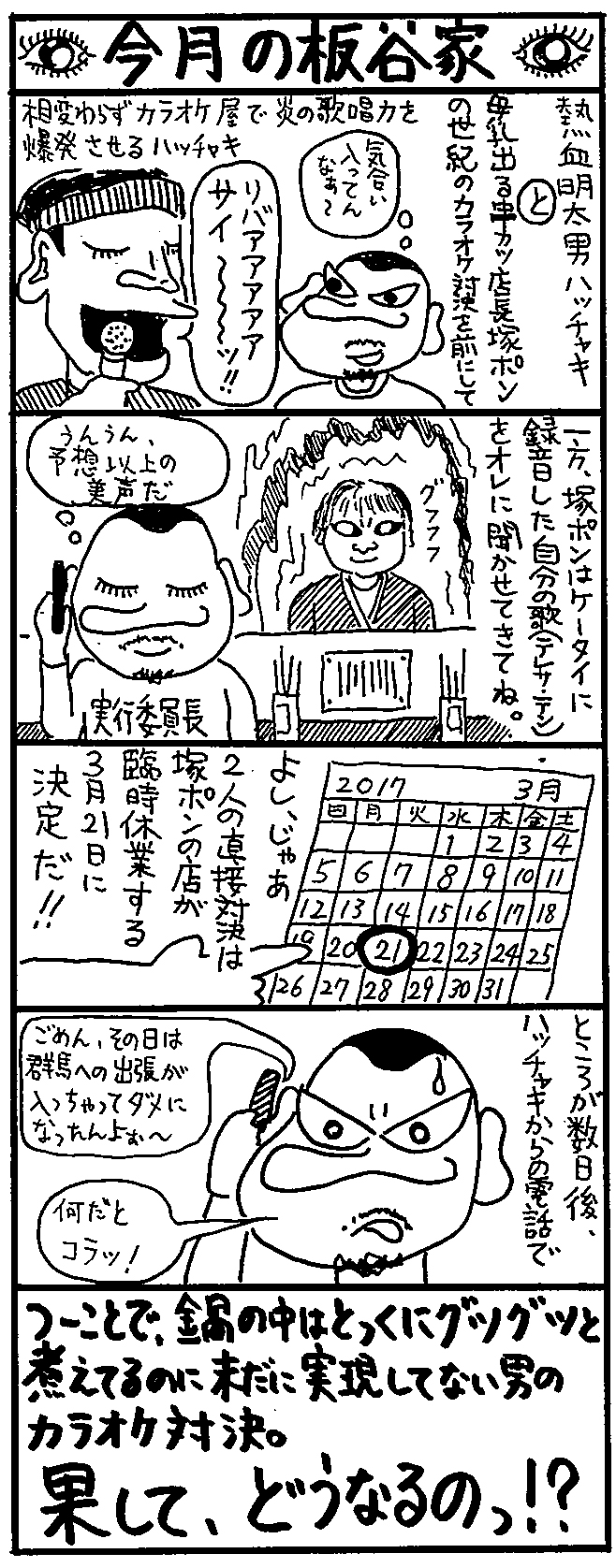初登板
20代の頃、一時期あるライター集団に在籍していたことがある。
いや、在籍といっても別に給料を貰ったこともなく、まともな仕事をしたこともなかったが、とにかく週に何日か、その集団が借りているマンションに通い、50~60代の上司たちが語るシナリオライターとは何ぞや、映画とは何ぞや、という話をひたすらに聞かされていたのである。要は、年を取って段々仕事が無くなってきたので、この際、若い奴らを自分たちの代わりに走らせ、そのギャラをハネようとしていたオヤジたちの集団に首を突っ込んでいたのだ。
ちなみに、その時の若い奴らはオレを含めて6~7人いたのだが、戦力になっていたのは、その若い奴らの中で1番年上の、確か当時27~28歳ぐらいの井上(仮名)という奴で、まぁ、戦力になるといっても月に1~2本のペースで30分番組の幼児向け戦隊モノのシナリオを担当しているだけだった。が、この井上は50~60代のオヤジたちには、やたらとペコペコしているのだが、オレたち若手達にはチビのくせにやたらと威張っていて、別にそのライター集団に大した思い入れの無かったオレは、正面切って何か言われたら速攻ブン殴って、その会社を去るつもりでいたのである。
そんなどうしようもない会社だったが、オレたちは丸っきり暇を持て余していたわけではなく、それは何でかと言うと、そのライター集団は草野球チームを作っていて、月に3~4回は他の草野球チームと試合をしていたのだ。ところが、場所は信濃町の神宮にある割といい球場を借りてやっていたのだが、オレらのチームは大概60代のジジイがピッチャーをやるので、いつもコテンパにやられてしまい、勝率は確か2割にも満たなかったのである。そして、必ずその負け試合の後で球場近くの小汚い居酒屋で皆で飲むのだが、前出の井上は年寄り連中のフォローをしつつも、実は自分も1回はピッチャーをやりたかったらしく、所々で「いや、だから今日の最終回の7回なんて、自分が喜んで敗戦処理投手になりますよ」とか「ウチは打撃に徹したチームになればいいんじゃないですか? 何だったら投げるのは自分が全部やりますし」といったプチアピールを頻繁に入れていた。
で、その甲斐あってか、そうこうしてるうちに井上が遂にオヤジたちからピッチャーに指名されたのだ。しかも、堂々の先発ピッチャーである。
その試合の井上の張り切り方は、とにかく尋常じゃなかった。試合は夕方の4時から始まるというのに、午前中の10時には既に球場の隅っこの方で1人でシャドーピッチングを開始してたらしく、オレたち若手組が15時過ぎに球場に行くと「遅せえぞっ、テメーらあああっ!!」と怒鳴り声を上げ、いつもはやらないのに1人で変なストレッチ運動をしたかと思うと、早くもマウンドに上がって延々とシャドーピッチングを繰り返していた。
そのうちオレもいつも守っているファーストの守備に着くことになったが、その近距離からマウンドにいる井上を見ているうちにある事に気づいた。キャッチャーに向かって投球練習をしている井上が、頻繁に一塁側のベンチの方に視線を送っており、それを辿ってみるとベンチの脇の木陰になっているところにジュディー・オングを20キロばかし太らしたような女、それがポツンと立っていたのである。
「あれって井上の彼女だろ?」
突然、真横からそんな声がしたので振り向いてみると、二塁手の長谷川というオレと同い歳の男がソッチのほうを見ながらニヤニヤしていた。
(そうか、今日は初めてのピッチャーだから、奴は彼女をこっそり呼んだんだな、クククク)
数十分後。ようやく響く審判の「プレイボ~~~~~~~~~~!!」の声。井上は背中を不器用に動かしながら一呼吸すると、バッターボックスのほうに振りかぶりながら第一球目を投げた。
バキンッ!!
なんとも言えない嫌な音だった。そんな音が井上が初球を投げたと同時に辺りに響き渡った。
「あがあああああ~~~~~~~~~っ!!」
次の瞬間、突然吠えながらマウンド上に崩れ落ちる井上。
(なっ……何があったんだよ!?)
そう思いながらも一塁ベースの脇にボーッと立ってると、主審を務めるオジさんが井上に近づいてって何かを話し掛けた後、大きな声で叫んだ。
「ダメだ、右肩の骨が折れちゃってるっ。投球骨折だ、これ!!」
5分後、若手の1人に左肩を担がれながら泣きながらマウンドを下りる井上。その様子を手も貸さずに見ていると、セカンドの長谷川が近づいてきながら次のようなセリフを吐いた。
「ったく、泣きたいのはお前じゃなくて、アッチにいる彼女だっつ--の」
2日後。オレは、井上の見舞いに行くのが面倒だったので、その会社を辞めた。