今年1番ビックリしたこと
オレは去年、同じ立川市内に住むクッチという9つ年下の男と仲良くなった。
キッカケは、まぁ、このクッチがオレの本の読者だったわけだが、ある日、オレが前年に書いたオフクロの日記を紹介した本についてツイッターにツイートしたら、このクッチが『自分の姉も同じ頃に白血病で他界しました』というツイートを入れてきて、それと立川の住人同士ということもあって、時々夕飯などを一緒に食いに行くようになった。
で、最初の頃、クッチはオレが連れていくラーメン屋やトンカツ屋の旨さに唯々感動している様子だったが、そのうち自分も知っている名店をオレに紹介したくなったらしく、何軒かのラーメン屋などに案内された。ところが、それらの店のメニューが何一つ旨くないのである。
てか、言っちゃあ何だが、オレはこの東京郊外の立川という街に50年以上住み続けているのだ。そこについ2~3年前に引っ越してきたクッチが、オレの知らない名店を紹介しますと言ったって、三多摩地区のそこそこ旨い食い物屋はオレも殆ど知ってるし、万一、タッチに連れられて行った店をオレが知らなかった場合でも、それらの店の名物の味は殆どが大したことはなかった。
『板谷さん。立川の隣の国立市に美味しいラーメンを食わせる店があるんですけど、今度お時間がある時にソコにいきませんか?』
今年の3月の、オレが車の免停を喰らっている時に、相変わらずクッチからそんなLINEが入った。
『何て名前のラーメン屋?』
オレは自分が既に知っているラーメン屋なら行かないつもりで、そう書いたLINEを返すとスグにクッチから返事があった。
『それは秘密です( ̄▽ ̄) 』
カチーン!ときた。てか、今回も恐らくオレが知っているラーメン屋に案内され、そこで敗戦処理のような食事をしなければならない確率が高いというのに、そんな余裕をブッ込んだような返事を返してきやがったのである。
(よし……)
オレは決心をした。そう、もしオレが知っているラーメン屋に案内しやがったら、その店の前でクッチのことを怒鳴ってやろうと思ったのである。
『じゃあ2日後の夕方5時半に立川駅の改札で待ち合わせしようぜ』
オレは、そう返事するとLINEを閉じた。で、2日後の午後5時半。時間通りにモノレールに乗って立川駅の改札に行ってみるとクッチは既にオレを待っており、2人で中央線の上り電車に乗って国立で降りた。
「板谷さん。飯を食う前に演劇を見ませんか?」
「えっ……演劇ぃ!?」
南口の改札を出たところで、クッチから突然言われた提案に驚きながらも、こんな空腹の時にそんなもん見てられっかよ!と思ったオレが、クッチに断りの文句を返そうとすると、
「演劇って言っても短いヤツですし、ココからタクシーに乗ればスグに着いちゃいますから行きましょう。もちろんタクシー代は自分が出しますんで」
そう言うと早々に目の前のタクシーに乗り込むクッチ。
(おいっ……)
10分後。既に真っ暗になった、国立駅から1.5キロほど離れた所でタクシーから降りると、さらに住宅以外は何もない寂しい路地に歩を進めるクッチ。
「なぁ、ホントにこんなところに劇場があんのかよっ? 人っ子一人歩いてねえじゃねいかよっ」
「いや、もう少しなんで」
さらに、その真っ暗な道を歩くこと数十メートル。不意にその道を左折すると、その少し奥にあるボロい民家の玄関の戸をいきなりノックするクッチ。
(おいっ、いきなり道に迷って誰かに尋ねようってんじゃねえだろうな?)
「はい………」
「あっ、先日、電話したものなんですが……」
「ああ、はいはい」
少しするとその玄関のドアが開き、ヒョロっとした体系の老人が顔を出した。そして、訳もわからずクッチに続いて家に上がり込むと、その老人に促されるまま、目の前の6畳間にあるコタツに腰を下ろすハメになるオレ。
「ちょっと待っててね、今、お茶を入れてくるから」
クッチとオレがコタツに脚を入れると、そう言って奥にある台所と思われる場所に老人は消えていった。
「おい、クッチ。何だよっ、あのジジイは? まさか、このクソ狭い家の中で劇をやろうってわけじゃねえよなぁ~!?」
「いや、ボクも詳しいことは知らないんですよ」
「はぁ!? じゃあ一体誰に、お前は演劇のことを聞いたんだよ?」
「いや、実は……」
クッチがそこまで言いかけた時、小さなトレーを抱えながら6畳間に戻ってくる老人。そして、テーブルの上にドロ沼のような色の液体が入った湯飲みを置いたかと思うと、自分もコタツに脚を入れて人懐っこそうな笑みを浮かべてきた。
「それは青汁の中に麦茶を混ぜたもので、まぁ、下品な味しかしないけど、体が温まると思うので良かったら飲んでみて下さい」
そう言って、再び人懐っこそうな笑みを漏らす老人。が、どうしてもオレたちは目の前の、その不気味な液体に口をつけることは出来なかった。
「あなたはドコから来たの?」
「えっ、オレっスか? と、隣の立川市ですけど……」
そう答えながらも、一体この老人は劇団の中でどんな役割をしてるのだろうか?という疑問がオレの頭の中をゆっくりと回っていた。もしかして、ホントに客の接待係なのだろうか? だとすると肝心の劇団員たちはドコにいるのだろうか?
その後、気がつくとオレは、その老人に自分は10年前に酷い脳出血を患って2カ月間も意識を失い、危うく死にかけたなんてことまで話していた。が、相変わらず、その痩せこけた老人はが何者なのかは全く分からず、そうこうしているうちにその老人がヨロつきながらコタツから立ち上がった。
「じゃあ、そろそろ始めますから、裏庭に出てください」
(えっ……)
何言ってんだろ、この痩せ侍は?と思った。そして、クッチの方に視線を移すと、奴も半笑いを浮かべながら首を捻っていた。
その後、オレたちはその老人が指示する通り、玄関に脱いでいた靴を持って、6畳間から突き出ているボロボロの縁側から外に出ると、すぐ左側に手作りの3人ぐらいが並んで座れる簡単なベンチがあった。
(おい、つまりココが客席かよ……)
そう思いながらも黙って同ベンチに座り、正面に向かって顔を上げた途端、今度は呆気に取られて口をポカーンと開けるしかなかった。その生垣に囲われた裏庭は10畳ぐらいの広さがあったが、その左端にはオレが腰掛けているベンチ以外は何も無く、右端の方にも木が1本立っているだけだった。が、その木が立っているスグ近くには浅い穴のようなモノが掘られていて、その真上には木の枝から吊り下げられた首吊り用としか考えられない輪っか状のロープがあったのである……。
ゴキュ……。
ほぼ同時に鳴るオレとクッチの喉。さらに次の瞬間、近くの草木がガサガサっと揺れたと思ったら、突然変なジャージを着た男が目の前に現れた。
(でっ……出たあああああっ!!)
もう少しで危うくそう叫びそうになった。が、そのジャージ男は、自分のズボンのポケットから財布を取り出すと、その中から千円札を1枚出し、それを家の出窓のところに置かれている小さな木の箱の中に入れると、身をかがめながらオレの前を通り、同じベンチの1番左端に静かに腰を下ろしたのである。
「あっ!」
突然叫び声を上げる、ベンチの真ん中に座っているクッチ。
「どっ……どうしたんだよ!?」
「いや、ボクたちもお金を払わないと……」
そう言うと、ベンチから立ち上がり、小さな木箱の中に千円札を2枚入れるクッチ。
「あっ、オレも払うよ」
そう言うと、首をゆっくり振りながら『いいです、いいです』というセリフを無音で吐き出しながら、クッチは再びベンチの中央に腰を下ろした。
「私の行為は、全部で約45分間です」
気がつくと、いつの間にか例の老人が縁側から裏庭へと出てきており、そんな一言をオレたちに吐いていた。
(つーか“行為”って何だよ!?)
心の中でそんなセリフを吐き出しながらも、さっきからモノ凄い勢いで腹の底から湧き出ている嫌な予感に煽られているオレがいた。でも、それって見せ物になるんかいっ!?
「なぁ、クッチ。このジジイは今から何をやるんだよ?」
嫌な予感に耐えられなくなり、オレをココに連れてきたクッチに小声で尋ねてみた。
「いや、自分も初めて見るんでわからないんですけど、でも、これって何かヤバいですよねぇ?」
クッチがそう答えているうちに既にジイさんの“行為”は始まっていた。ジイさんは奥の木に向かって歩き始めていたが、その速度がとにかくノロかった。いや、もっと正確に言うと太極拳の動きを更に10倍ぐらいノロくしたような、とにかくそんな足取りで奥の木に向かって超ゆっくり動き始めたのである。
約20分後。ようやく木の枝から吊り下がる、問題のロープの前に立つ老人。
(おい、遂にかよ……)
3月上旬の夜の寒さ、それと嫌な予感に同時に煽られ、オレの体は密かに震えていた。
円状になったロープのを2本の腕でシッカリとつかむ老人。てか、その時オレは、この人のことを自分は70歳ぐらいの老人だと思っていたけど、実は、まだ60代前半ぐらいなんじゃないかと思った。
グシィ!!
唐突にロープの中に首を入れると、足元の土を蹴って宙ぶらりんの状態になる老人。ホントに久々のことだが、その光景を目にしている自分は今、夢の中にいるんじゃないのかと思った。首をマジで吊っている老人。そして、それを6~7メートルほど離れたところから静かに見ているオレたち。……どう考えてもマトモな光景じゃなかった。
老人が首を吊り始めてから2分ほど経った頃だった。ゆっくりと上着のポケットからケータイを取り出すクッチ。
(まさか………)
が、そのまさかだった。クッチはケータイをカメラモードにすると、首をくくっている老人の方にレンズを向け
パシャ!
1回だけ静かにシャッターを押した。
老人が首を吊り始めてから約5分後。再び両手でロープをつかんだかと思うと、そこから一気に首を外し、そして、ゆっくりと地面に足を着けた。で、またしても約20分かけて超ノロい太極拳のような動きでコチラに戻ってきた老人は「はい、終了」と言うと、ようやく普通の動きに戻った。
その後、オレは思いきって縁側に腰を下ろした老人にいくつか質問したところ、意外にも彼は割と丁寧に答えてくれたのである。
まず、この首吊りパフォーマンスは、もう20年ぐらい前からやっており、ロープが首元にシッカリ入っちゃうとホントに死んでしまうので、アゴの下で全体重を支えられるように訓練として首吊りは1日5回やっているらしい。また、このようにお金を取って首吊りを見せるのは月に3~4回程度だが、この先、どんなペースでやっていくかはハッキリとは決めていないという。
で、肝心の「何で首吊りなんかを人に見せているのか?」という質問には、若い頃は人があまりやらないことを5つぐらいやっていたが、その中でもこの首吊りは1番やらないだろうから、ある年齢になってからパフォーマンスの内容を首吊りだけにしたとのこと。今までにロープが首元にガッチリ入っちゃって死にかけたことは5回ぐらいあるらしい。そして、何でそんな危険なことを続けているのかと改めて問うと、自分にはコレが1番合った職業だからと言う。
で、そんなやり取りをした後、老人が家の中に入っていったのでクッチに「じゃあ、帰ろう」と促すと、彼は家の中に向かって「すいませ~ん、じゃあ、ボクたち帰りまぁ~す!!」と叫んだ。と、何かビニールの袋を破るような音がした後、「今、インスタントだけど焼きそば作るから食べてかない?」というセリフが返ってきた。が、オレはその時、腹の底から湧き出ているものが、今度はグロテスクな嫌な映画を観た後のような重度のむかつきに変わっていて、とにかく一刻も早く立ち去りたかったので、「この後、友達と御飯を食べる約束があるので、すいませぇ~ん!!」と言って、その家の敷地から出ることにした。
「実はウチの嫁がインターネットをやってて偶然見つけたみたいで、あの老人は〝首くくり栲象(タクゾウ)"って名前らしいんですが、私は怖くて見に行けないからアナタが今度見てきてよ、って嫁に言われてたんですよ」
「………………………」
「それで、なら、板谷さんを誘ったら喜ぶかな、と思ったんです」
栲象の家から300メートルほど離れたところにある中華屋で、そんな話をしながら童顔のクッチはチャーハンや餃子を楽しそうにゴリゴリと食べていた。
てか、首吊りシーンをケータイで撮り、さらにそれを見た後でも何にもなかったかのように食欲を爆発させているクッチ。ふと、仮にコイツがコロンビアの貧しい家庭の7人兄弟の末っ子あたりに生まれてたら、笑いながら平気で人にマシンガンをブッ放すような男になるだろうな、と思った。
退屈な食堂しかオレに紹介しない男が、いきなり投げてきた超剛速球。いや、とにかくビックリした……。
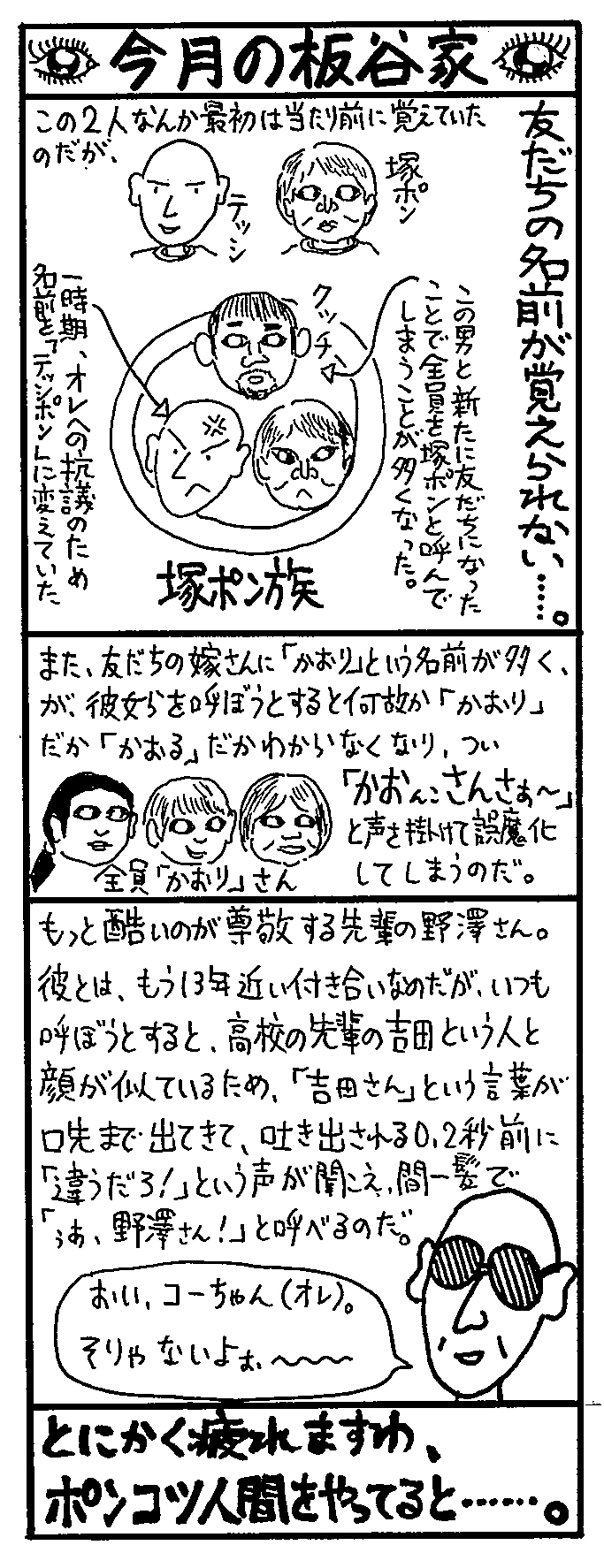
『そっちのゲッツじゃないって!』12/7発売決定!!
ガイドワークスオンラインショップからのご購入でゲッツ板谷のサインが抽選であたり、もれなく西原理恵子表紙イラストのクリアファイルが付いてきます!
(※ご購入の単行本にサインが入ります。サイン本は発売日以降のお届けになります)
◇ガイドワークスオンラインショップ
『そっちのゲッツじゃないって!』
◇amazon
『そっちのゲッツじゃないって!』


