今年オレを一本背負いした女
さて、2019年もあと僅かで終わりである。
今年もオレが応援しているプロ野球の埼玉西武ライオンズは、去年に引き続きペナントレースで優勝したにもかかわらず、その後のクライマックスシリーズで2位だった福岡ソフトバンクホークスにスイープされ、2年連続で涙を飲むことになった。そんな悔しいシーズンだったが、嬉しいことも1つあった。
今から10年前、オレがライオンズのファンになりたての頃、その試合を見に西武ドームに行くのは基本的にオレ1人だけだった。何試合に1回かは後輩のシンヤくんや友達のハッチャキが一緒に来てくれたが、基本は1人で応援に行っていたのである。ところが、それから5年ほど経って、たまこちゃんという8つ歳下の友達を西武戦に誘ったところ、彼女も幼い頃に西武ファンの父親に時々西武球場に連れられて応援に行っていたこともあり、瞬く間に本気の西武ファンとなり、それからは7~8割方の試合を彼女と見に行くようになった。
しかも、たまこちゃんは3年目からはセンターを守っている秋山翔吾選手が特に好きになり、会社の休み時間とかには頻繁にパソコンとかで西武ライオンズの情報をチェックしているので、オレの方が逆にたまこちゃんからライオンズの情報を教えてもらうことが多くなっていたのである。そう、当たり前の話だが、何かのスポーツチームや何かの音楽グループなどを一緒に応援するには当然のごとく、自分もそのチームやグループのことが本当に好きでなければ、すぐに応援に行くのが面倒臭くなってしまうのだ。
で、オレには、その応援友達も出来て喜んでいたところ、今年になってたまこちゃんが好きな秋山翔吾選手が来シーズンは西武とは契約せずにメジャー・リーグに行く可能性が濃厚になってきた。当然、その話題が出ると急に寂しそうな表情になるたまこちゃん。オレは(う~ん、何とか彼女を元気づける手立てはないものか……)と考えていたところに、今年になって割と頻繁にツイッターでDMなどを交わすようになっていた“ミホにい”というオレと同い年のオバちゃんが、どうやらサッカーだけでなく野球にも興味があるということがわかってきた。
オレは考えた末、そのミホにいを今年5月の西武戦に誘った。そして、西武ドームの観客席に横並びに座るオレ、たまこちゃん、ミホにいの3名。で、どうなったのかと言うと、ミホにいがでしゃばらないんだけど人に細やかな気が遣えるたまこちゃんのことを大変気に入り、また、たまこちゃんの方もビックリするほど野球のことを知っていて、しかも、シャキシャキした性格のミホにいのことが好きになっていたのである。
こうしてオレは、また1人、西武ライオンズ応援仲間を増やすことが出来たのだが、某大手企業に勤めているというミホにいに遅まきながらあることを訊いてみた。
「ねぇ、何で“ミホにい”って呼ばれてるの? てか、ミホっていうのは名前から来てるのはわかるけど、『にい』って何?」
「ああ、女なんだけど男っぽいって意味よ。私もいつ頃からか、そう呼ばれるようになったのかはわからないけど」
「てか、ミホにいって、どんな仕事してんの?」
「ほら、私が勤めてるような大企業って、必ず身体や精神に障害を持ってる人を何十人か雇うって決まりがあるのよ。で、早く言っちゃえば、私はこの部署の課長なの」
「へぇ……何だか凄いねぇ」
「ちっとも凄くなんかないわよ。ただ、障害を持って精神的にも不安定な人たちにヤル気を持ってもらうっていう仕事だから、根気だけは必要だけどね」
「ふぅ~ん………」
オレはその時、ミホにいは結構大変な仕事をしてるとは思ったけど、正直“男っぽい”と見られてることについては舐めて捉えていた。てか、そういう障害を持った人達を時には怒鳴ったり、また上司に対しても理にかなわないことを言われれば言い返すことぐらいは出来るだろうと思ったが、例えばバス停に並んでいる時に前の男と取っ組み合いのケンカをするとか、ヤクザに因縁をつけられても一歩も引かないといった、そこまでの無鉄砲な男らしさは無いだろうと思ったのだ。ま、当たり前だけどね(笑)。
で、その後もオレとミホにいはたまこちゃんと予定が合う時は3人で、また、たまこちゃんの都合は悪いがミホにいの都合がいい時は2人でも西武ドームに行くようになった。そして、そんな時にミホにいから彼女の2人の子供たちの話を聞くと、もうそれだけでも彼女は子供たちを心から愛し、また子供たちもまるで友達のようにミホにいに愛情を持っていることがわかった。
オレはそんな話を、しかも、自分と同し年の友達から聞くと堪らなくなった。そう、ウチの一人息子は未だに反抗期にいるらしく、オレに対しては遊んだり一緒に飯を食いに行くことも殆どないし、普通に落ち着いて会話することも避けている節があるのだ。で、ある時、あまりにもうらやましかったので、オレはミホにいに自分の妹の話をした。
以前、自分の本にも少し書いたことがあるが、オレの妹にはオレの息子と同い年の娘がいて、その子は重い自閉症を患っていた。が、オレの妹はなかなかその事を認めることが出来ず、娘を普通の小学校に入学させた。もちろん、その小学校の先生たちとは何度も話し合ったが結局、オレの妹は送り迎えだけではなく、娘が小学校にいる時もズーッと同じ教室にいて、そんな生活を遂に6年間も続けきったのである。その上で娘をようやく特殊クラスのある中学校に入れたのだ。
オレは、その話をミホにいに少し得意な気持ちになって喋った。そう、6年間も娘と同じ小学校に通い続けたオレの妹の精神力は凄いだろう、と。そして、ミホにいはそんなオレの話を黙って聞いていたのである。
それから数カ月後。オレとミホにいは再び2人で西武戦を見に行く機会があり、その後、たまこちゃんと西武戦を見に行った後でもそうしてるように、そのまま友達の塚ポンがやってる串カツ屋へ直行した。
「この前、たまたま弟のセージが名古屋から帰ってきてね。2人で酒を飲んでる時にオレが『しかし、妹の娘が自閉症を患った原因って、やっぱり旦那の方の家系にあるような気がするんだよな。お父さんもかなり変わった人だったって話だし、ひょっとすると隔世遺伝みたいなもんじゃねえかなぁ~?』って言ったら、セージの奴も……」
「ちょっと待って!」
串カツ屋のカウンターで話している最中、オレの話を途中で止めるミホにい。
「この前は言わなかったけど、板谷さんの妹の娘が自閉症を患ったことって、むしろ私は妹さんの方に問題があると思うよ」
「はぁ~!?」
「障害を持った子供がいる身内の人は、あの子がああいう障害を負ったのは相手側の家系のせいだって言うことが多いけど、板谷さんの妹の娘さんのケースは多分妹さんの影響が大だと思うよ」
気がつくと自分の手がワナワナと震え始めたのがわかった。オレと妹は昔から特に仲が良かったという訳ではなかったが、しかし昔、オレが嫁の実家に娘さんを下さいと挨拶に行った際、嫁のお母さんに「板谷さんの妹さんは何をなさっているんだっけ?」と尋ねられ「某大手料理学校の新宿校の副校長をしてます」と答えた時に、その場にいた嫁の親父が「くっだらねぇ~」と言ったのを聞いて、もう少しで嫁の親父さんを半殺しにするところだった。そう、昔から自分のことを悪く言われてもそこまで腹は立たないが、とにかく不器用なくらい真面目で堪え性のある妹のことを悪く言われると、オレは自分でも信じられないくらい頭に血がのぼるのだ。そして、その時、ミホにいはオレの妹の娘が自閉症を患ってる原因は妹にあると思う、と言ったのである。
「何でオレの妹の方に問題があるんだよっ!?」
自分でもビックリするような大きな声で、そう尋ねていた。が、ミホにいはそれに全く臆することなく言葉を続けた。
「いや、前に板谷さんは私に妹が自分の娘を一般の小学校に通わせるために、自分自身もその小学校に丸々6年間通ったって言ったことがあるよね」
「ああ、言ったよっ。それがどうしたんだよっ!?」
「妹の娘さんって重い自閉症で、言葉も満足に話せなかったんでしょ? 普通なら一般の小学校に入学させても、せいぜい3~4日、長くても2~3週間で、やっぱ同じような病気を患ってる子供がいる小学校の方へ転校させてくださいって学校側に言うんだよ」
「何でだよっ? ウチの妹は自分で責任を負うって言ったんだぞ。そしてそれを全うしたんじゃねえかっ!」
「でも、それは妹さんだけの気持ちの問題だよねっ!?」
声を荒げるオレに一歩も引かないミホにい。
「自分の娘を一般の小学校に通わせたい。その気持ちはわかるよ。だけど妹さんは割とすぐにわかったはずだよ。自分の子供が他の子たちとは明らかに違うって。でも、学校側に自分の意見を押し通しちゃったこともあって、いいや、なら自分が我慢すればいいんだってことで、6年間も小学生たちと一緒のペースで学校に通ったわけでしょ」
「だからそう言ったろっ」
「妹さんはそれで自分の欲求が通ったからいいけど、じゃあ、妹さんの子供はそれで楽しかったのかなぁ? 自分の周囲のクラスメイトはみんな楽しそうに話してるのに、自分だけは何でかその会話が出来ず、しかも、途中からは誰も自分に話し掛けてこようともしない学生生活をどう思ったかな? あと彼女とクラスメイトだった小学生たちは、妹さんの娘は置いとくとしても、そんな自分たちの母親と同い年ぐらいのオバさんが、常時自分たちの教室にいるって日常は嫌じゃなかったかな?」
「そ、それは……」
「確かに、妹さんの自分の娘を思う気持ちはハンパじゃないし、そんな重い自閉症の子供を普通の小学校に6年間通わせたってことは、ある意味、尊敬に値するよ。とても真似できないよ」
「……………」
「でも、普通の人は、仮にそうやって自分の欲求を押し通しても、やっぱりそれと同時に肝心の本人はどうなのか、また、その周囲はどうなのかって考えるんだよ。それが大人でしょ。だって、この世の中、自分と自分の娘だけが生きてるんじゃないんだから」
ズッダアアア~~~~ン!!
突然、そんな衝撃に貫かれた。それは、オレが自分の半分ぐらいしか体重の無い女に一本背負いを食らった音だった。
オレのオフクロが生きていた頃、よくそのオフクロと妹は口喧嘩をしていた。当時は、女同士だったし、2人の性格が似ているから逆にぶつかり合うんじゃないかと思っていたが、今、冷静に考えると、アレは自分の周りを冷静に見ることができる者と出来ない者との喧嘩のような気もしてきた。
ウチの近所の職員の数だけでも200名を超える老人ホーム、そこにいる4人の園長の1人として働きに出ていたオフクロは家の中で妹と言い合っている時、頻繁に「もっと周りのことも見なきゃダメだよ」という言葉を吐いていたことを思い出した。そして、オフクロは、そんな妹の物凄い真面目なんだけど1点しか見られない性格、そして妹の娘のことを心底心配して67という若さで他界していったのだろう……。
時々野球を見に行くようになってまだ1年も経っていないのに、オレがキレて暴れるんじゃないかという可能性も恐れず、友達として言わなくちゃいけないことを言わなくちゃいけないタイミングで口にしてくるミホにい。
うん、確かに彼女の中には「本物の男」がいるな。ごめんなさい、もう舐めません(笑)。
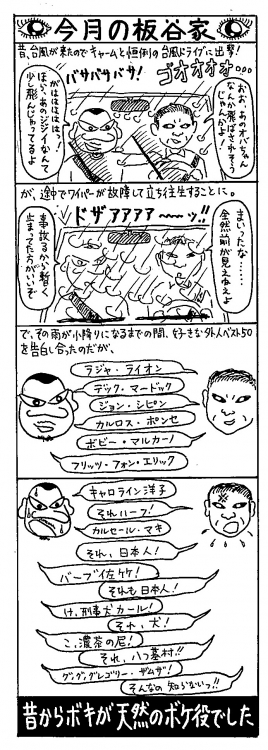
『そっちのゲッツじゃないって!』発売中!!
◇ガイドワークスオンラインショップ
『そっちのゲッツじゃないって!』
◇amazon
http://amzn.to/2xLez35


